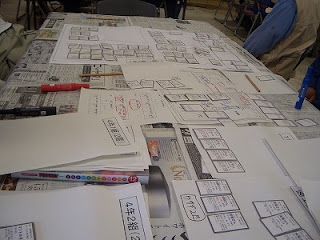防災講座を開催してきました。
9月30日(土)に最終回の第三回目を開催しました。
第1回は地震、
第2回は水害、土砂災害の知識を学びました。
第3回は、「避難所の作り方、運営方法を学ぶ」とし、
避難者の受入や配置、避難所で起こる様々な出来事を
ゲーム感覚で学びます。
講師は防災危機管理課の方々です。
避難所運営ゲーム「HUG」を使い、
避難所を開設し、運営していくゲームです。
真冬の午後、大地震の発生です。
小学校で避難所を開設しなくてはなりません。
 |
カードに次々と起こる事案が書いてあり、
それを一つずつ処理をしていきます。
例えば・・・
「明後日ポータブルトイレが30個、届きます」
「避難者北地区、 自宅全壊、家族4人と犬2匹、父38歳、母36歳、姉8歳、弟6歳」
「避難者南地区、 自宅半壊、夫婦 夫85歳、妻84歳、夫は認知症」
「避難者 バス旅行中被災、東名高速道路から歩いて避難所へきた」
などなど、次々と避難者がきたり、指令があります。
それをどのように対応し処理していくか、
みなさん頭をひねりながら、抱えながら・・・
ゲームが進みます。
さらに条件は過酷になり、
電気、水道は不通。
下水道は不明です。
時は刻々と過ぎ、暗くなり始めました。
電気はつきません。
トイレ水も流れません。
下水管も不明と言うことで、
例えばプールの水でバケツの水で流しても、
もしかしたらそのうちあふれてしまうかも・・・
みなさん頭を抱えてしまいました(T_T)
さらに次々と避難者がやってきます。
「避難者南地区 自宅半壊、家族4人とウサギ2羽。
父、母、子供2人、うち1人がぜんそくの発作で治療が必要」
「近所の○○工場、避難所として工場を開放しているが、
50人分の食料と毛布を要望」
次々と起こる出来事を処理していかなければなりません。
それでも、ゲームを進め、
みなさんもお互い積極的に意見を出し合うようになり、
次第に事案の処理が早くなってきました。
防止危機管理課の方にアドバイスをもらいながら、
様々な世代の方の意見やアイデアも出てきます。
「避難者南地区、 幼児2人。両親は不明。近所の人がつれてきた。」
というカードには、
近所の顔見知りの方のそばに配置して、みんなでみてもらったらどう?
など、意見を出し合い進めていました。
また体調を崩している人や、感染のおそれのある人などは、
体育館ではなく、教室を利用するように考えました。
ゲーム終盤の頃には、
校庭の敷地内の様々なところに気付き、
工夫して対応する意見も多かったです。
災害への備え、災害への対応は、
実際に起きてみないと分からないですが、
今回の講座で少しでも災害について考える機会を持ったことは、
もしものときに、ずいぶんと役に立つのではないでしょうか。
皆さん、とても真剣に取り組んで頂きました。
ご参加された皆さま、大変お疲れ様でした。
今回の講座を期に、災害に対する備え、対応を
地域みんなで考えていけるといいなと思います。